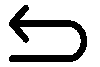171 岡山県 吉備の中山 穴観音
【Introduction of Iwakura171】Visit・Photo:2019.5.4/Write:2025.5.03

□分類:石仏・摩崖仏(非イワクラ)
□信仰状況:民間に信仰されている。
□岩石の形状:岩群、5個の岩石
□備考:人工物、仏像が彫られ、穴が穿たれている

□住所:岡山県岡山市北区吉備津
□緯度経度:34°40'01.57"N 133°51'18.36"E
(googleに入力すれば場所が表示されます)
吉備の中山の中山茶臼山古墳は全長105mの前方後円墳で、彦五十狭芹彦命の墓といわれており、孝霊天皇の皇子であるため宮内庁が管理しています。
その後円部の東に穴観音があります。次のような看板が掲げられています。「主石と考えられる自然石(花崗岩)の正面を船形に彫り沈めて仏像を半内に現し、石の左側面には口径20センチ、深さ16センチ、底径4センチほどの穴が窺われるが、仏像も穴も現状が判らぬ程風化し痛みも烈しい。昔からの言伝えで側面の穴に耳をあてると観音様のお声が聞こえると言う俗信仰があって、昔から縁日には参拝客が多い。私見ではあるが、この岩石群は茶臼山古墳の築造時(五世紀頃)からこの位置にあり、原始的祭祀行事の場と思われ、正面の仏像は観世音菩薩ではなく大日如来像である----- 一宮地域活性化推進委員会。」
5個の岩石に赤い布が掛けられていて、その一つの石には仏像のレリーフが彫られており、横に20センチの穴があることから、穴観音と呼ばれています。
この穴観音については、2つの考え方が提示されています。一つは直ぐ西側にある中山茶臼山古墳の遥拝所であるというものです。もう一つは、南東にある八徳寺の奥之院であるという薬師寺慎一氏の説です。
八徳寺については、『一品吉備津宮社記(明治)』に「波津登玖神社 小祠 此地今属備前国 祭神温羅命」と書かれており、この「波津登玖神社」が「八徳寺」の前身であると考えられます。その波津登玖神社に温羅が祀られていたと書かれています。また、八徳寺の北東250メートルの位置にある石舟古墳は、室町時代には温羅の墓と考えられており、桜の枝に水をかけて花弁が散るまで互いに打ち合うという温羅の花祭りが3月3日に行なわれていました。このように、八徳寺は温羅との関わりが深い場所です。「温羅」という名前が登場したのは江戸時代であることは【Introduction of Iwakura168】で述べましたが、温羅つまり吉備の本来の支配者にとって、この八徳寺の場所が重要であったと考えられます。
さて、この穴観音は、自然の景観ではなく、人工的に岩石が寄せられています。前述した2説は、この岩石群を磐座と見ているのですが、違う見方もできると思います。石の横の穴は何かの構造物に使用するために穿たれものと考えると中山茶臼山古墳を建造するための岩石の集積所であった可能性が高くなります。後世、その岩石に仏像が彫られたので、信仰が生まれたのではないでしょうか。
現在は、穴観音として民間に信仰されていますが、信仰の対象は岩石ではなく仏像ですのでイワクラではありません。したがって、石仏・摩崖仏(非イワクラ)に分類しました。
#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #巨石文明 #古代文明 #岡山県 #岡山市 #吉備津彦神社 #吉備津彦神社 #備前 #備中 #中山茶臼山古墳 #穴観音 #八徳寺

本ページのリンクおよびシェアは自由です。
最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

[さらに詳細な情報]