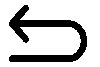172 岡山県 吉備の中山 環状石籬
【Introduction of Iwakura172】Visit・Photo:2019.5.4/Write:2025.5.10

□分類:自然岩石(非イワクラ)
□信仰状況:信仰の形跡なし。
□岩石の形状:岩群
□備考:高原美忠氏が環状石籬と名付けた。

□住所:岡山県岡山市北区吉備津
□緯度経度:34°40'09.43"N 133°51'22.74"E
(googleに入力すれば場所が表示されます)
吉備の中山の尾根の八畳岩の近くには、数十個の岩石が存在する場所があります。1935年にこの地を訪れた皇學館大学長の高原美忠氏は、この岩石群を「環状石籬(せきり)」と名付けました。環状石籬とは、環状列石、つまりストーンサークルのことで、人工的に円状に並べられた岩石群を指します。しかし、この辺りの岩石に関して人工的に並べられた様子はみられません。また、過去に祭祀が行われた形跡もなく、現在も信仰されていないため、自然の岩石群と考えられます。
また、この他に吉備の中山の尾根部には、鏡岩、お休み岩、夫婦岩遺跡などの名前が付けられた岩石もありますが、これらも最近に名前が付けられたものであり、自然の岩石群と考えられます。
特に、環状石籬、鏡岩、お休み岩、夫婦岩遺跡といった岩石が、吉備の中山の麓に住み吉備の古代史を研究した薬師寺慎一氏の書籍(2001~2012年)に登場していません。このことは、これらの岩石が古代祭祀跡ではなく、名前の付いた自然の岩石であることを示しています。
では、吉備の中山にストーンサークルは存在しないのかというと、そうではありません。『吉備津神社境内絵図(江戸)』に、11個の石が円状に並んでいる様子が描かれており「内宮石」と記載されています。場所は、吉備の中山の西のピークである飯山の中腹になります。平安時代には、吉備津神社(備中)は、正宮、本宮、新宮、内宮、岩山宮という吉備津五所大明神から形成されていました。ちなみに内宮の御祭神は、大吉備津彦命の妻である百田弓矢比売命です。
この内宮は社殿がないストーンサークルでしたが、1690年に社殿が建てられ、1910年に本宮に合祀されました。1989年に薬師寺慎一氏は吉備津神社(備中)の許可を得て、山中に分け入り、社殿の廃材と数個の石を発見しています。
ストーンサークルの位置に神社が建てられるという形は、吉備津神社(備中)から北西に2.5キロメートルの位置に鎮座する真宮神社【Introduction of Iwakura 64】でも見られ、この地方には岩石で円形に囲むという祭祀形式が存在したと考えられます。
#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #巨石文明 #古代文明 #岡山県 #岡山市 #吉備津彦神社 #吉備津彦神社 #備前 #備中 #環状石籬 #環状列石 #ストーンサークル #鏡岩 #お休み岩 #夫婦岩遺跡

本ページのリンクおよびシェアは自由です。
最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

[さらに詳細な情報]