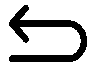174 岡山県 吉備の中山 岩山宮
【Introduction of Iwakura174】Visit:2016.8.13/Photo:2025.2.23/Write:2025.5.24

□分類:磐座(狭義の磐座)
□信仰状況:神社に祭祀されている。
□岩石の形状:不明、岩単体と推測
□備考:岩石は社殿の中にあり見ることはできない。

□住所:岡山県岡山市北区吉備津
□緯度経度:34°40'11.28"N 133°51'03.66"E
(googleに入力すれば場所が表示されます)
平安時代には、吉備津神社(備中)は、正宮、本宮、新宮、内宮、岩山宮という吉備津五所大明神から形成されていました。
この中の岩山宮は、比翼入母屋造の正宮から南に100メートル山を登った場所に鎮座している社殿です。
五所大明神の正宮には大吉備津彦命(彦五十狭芹彦命)、本宮には大吉備津彦の父(孝霊天皇)、内宮には大吉備津彦の后の百田弓矢姫命、新宮には大吉備津彦の弟の孫である吉備武彦命というように、大吉備津彦の一族を御祭神として祀っているのに対し、岩山宮は大吉備津彦命と関係のない建日方別神(たけひかたわけ)を御祭神としており異質です。『一品吉備津宮社記』によると岩山宮の御祭神は、「中山主命、建日方別命」と書かれています。この「中山主命」とは、吉備の中山の地主神を意味していると考えられます。「建日方別」については、『古事記』の国生み神話において、伊邪那岐神と伊邪那美神が吉備の児嶋を生んだときに、その別名として「建日方別」が登場しています。
神社の旧記には、「摂社の岩山大明神は、吉備の中山の地主神で巌を祀る」と書かれており、この岩山宮の中には岩石が祀られていると伝わります。その岩石は見ることはできませんが、社殿の大きさから小さな石ではなく、少なくとも1メートル以上の岩であろうとは想像できます。このような祭祀方法もまた異質です。
そして、この岩山宮から東に200メートル登った中山の中腹に金比羅宮跡があります。『吉備津神社境内絵図(江戸)』には屏風上の巨岩が描かれており、これもまた岩石を祀っていたと想像できます。そして、さらに200メートル登った中山の頂上に八畳岩があります。八畳岩は【Introduction of Iwakura 9】で紹介したように、古代祭祀が行われていた磐座です。この八畳岩―金比羅宮―岩山宮は、大神神社等で見られる奥津磐座―中津磐座―辺津磐座であり、吉備の中山の中央部から西に向かう東西の磐座祭祀ラインとなります。著者が提唱する「磐座から神社への変遷説」は、山の上の山宮から麓の里宮そして生活の場である田宮へと祭場が移動するにつれて、磐座祭祀から神社祭祀へと変貌していったという説ですが、八畳岩の磐座が山宮にあたり、金比羅宮から岩山宮へと山を降っていますが、岩山宮はまだ山の麓ですので、里宮という事になり、田宮へと変遷する前に祭祀ラインが途絶えたと考えられます。その磐座の祭祀ラインを断ち切った証拠が岩山宮の祀り方であり、磐座を社殿内に閉じ込めて封印したのではないかと推測します。
そして新しく設定された祭祀ラインは、現在の正宮を参拝する時の方向です。この比翼入母屋造の正宮は1425年の室町時代に建てられたもので、それ以前の正宮の様子については、1304年の都人の紀行文に「御殿のしつらいも社などはおぼえず、様変わりたる宮ばらていに、几帳などの見ゆるぞめずらしき」と書かれ、鎌倉時代に風変わりな様式であった事はわかりますが社殿の方向はわかりません。なお、吉備津神社(備中)の創建については不明です。852年に朝廷から四品を授かっていますから、少なくとも平安時代前期には存在していました。
現在の比翼入母屋造の正宮は北北東を向き、吉備の中山の南西のピークである飯山を向いています。さらに飯山の向こう側には新宮があります。つまり正宮―本宮―飯山―新宮の飯山祭祀ラインです。なお、神社本殿の後ろ側は閉じられて神様のために暗を形成するのが通常ですが、不思議なことに、吉備津神社の正宮の南側には扉が付けられています。これはこの飯山祭祀ラインを意識しているとしか考えられません。
では、なぜ東西の磐座祭祀ラインを南北の飯山祭祀ラインに変更したのか、それは、「温羅伝説」の一つである『吉備津宮勧進帳(1583年)』において、吉備冠者が降参するときに自分の名を五十狭芹彦命に献上する場面に象徴されていると思います。
「日本の天皇の領土を侵略するという過ちを犯した冠者は、一宮彦命に降伏を申し出て、次のように言った。「本当の勇士たる者は、死を恐れない。ただ、武士の名誉を失うことのみを心配する。恐れながら願わくは、私の名前を貴方・一宮彦命にお譲りたてまつる。貴方はこれより西国を領せよ。今、貴方の位は征夷将軍であるが、みずから奪い返した領土の名称にちなんで、これより以降、一宮彦命は、お名前を一宮吉備津彦大明神と号されよ。」(中山薫、「温羅伝説」2013、より)
吉備の中山を支配していたのが「吉備冠者(温羅)」であり、東西の磐座祭祀ラインを使用していましたが、そこに五十狭芹彦命が侵略してきて吉備を奪い「大吉備津彦」と名乗りました。そのときに、これまでの吉備冠者(温羅)の政祭体制を否定するために、吉備冠者が使用していた磐座祭祀ラインを封印し、南北の飯山祭祀ラインに変更したのではないでしょうか。なお、封印した東西の磐座祭祀ラインを伸ばした西端に御竃殿が設けられているのも意味深です。
これと同じような祭祀ラインの変更は諏訪大社の本宮でも起こっています【Introduction of Iwakura 11】。守屋山へ向かう磐座祭祀ラインが、神居に向う方向へ90度変更されました。諏訪の地は、洩矢神を祀る洩矢族(後の守矢氏)が支配していましたが、出雲から来た建御名方神に取って代わられます。
#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #巨石文明 #古代文明 #岡山県 #岡山市 #吉備津彦神社 #吉備津彦神社 #備前 #備中 #岩山宮 #建日方別神 #中山主命

本ページのリンクおよびシェアは自由です。
最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

[さらに詳細な情報]