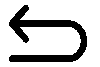184 奈良県 三輪山 平等寺の影向石
【Introduction of Iwakura184】Visit・Photo:2013.4.29/Write:2025.8.15

□分類:磐座(狭義のイワクラ)
□信仰状況:寺院に祭祀されている。
□岩石の形状:岩組、ドルメン
□備考:人工物

□住所:奈良県桜井市三輪
□緯度経度:34°31'36.525"N 135°51'16.936"E
(googleに入力すれば場所が表示されます)
大神神社から南に200メートルのところに平等寺があります。寺伝では、581年に聖徳太子が賊徒を平定するために三輪明神に祈願して建立した大三輪寺となっていますが、明確に資料に現れるのは鎌倉時代です。慶円が三輪神社の傍らに建てた真言灌頂の道場である三輪別所が平等寺の前身と考えられます。慶円禅観上人は、三輪明神の影向をうけ神道灌頂之秘法を授けられたと伝わっています。神仏習合の一派である三輪流神道が生まれ、江戸時代には、本堂をはじめとする七堂伽藍のほか12坊舎が存在するほど繁栄しました。
大神神社には平等寺、大御輪寺、浄願寺という3つの神宮寺がありました。
6世紀に日本に公伝した仏教は現世利益をもたらすものとして受容され、国民にも広がっていくと、神と仏の関係を説明する必要が生じました。そこで僧侶側から論じられたのが神身離脱説です。神々も輪廻の中で苦しむ存在であり、その神々を解脱に導くために神宮寺が神社の境内に建てられるようになりました。10世紀には、本地垂迹(ほんじすいじゃく)説が生まれ、神々は仏が民衆を救うために現れた仮の姿であると主張して神を権現(ごんげん)と呼んで、仏教が神様を上書きしてしまいました。
この平等寺も鎌倉時代から江戸時代まで大神神社の別当寺となり、平等寺の僧侶が大神神社の社事を仏式で行って、神社を支配しました。
明治時代となって神仏分離令が発せられると、それまでの神社側の反発が噴出して廃仏毀釈が勃発します。この平等寺も堂舎が破壊され仏像もなくなりましたが、1977年に曹洞宗の寺院として再興しました。
この平等寺の不動堂の裏にドルメン状の人工の岩組が残っています。平等寺のホームページには「影向石、神のよりしろとされた岩。三輪明神が貴女の姿になってこの石上に現れ、慶圓上人と問答をなされたと伝えられる。現在の場所へは当時地元で一番の力持ち、松田楢さんが運んだと伝えられる。」と書かれています。
鎌倉時代に慶円上人が三輪明神と邂逅した岩石と伝わっていることから狭義の磐座に分類しましたが、この岩組についての古い記録は見当たりませんので、新しい岩組である可能性もあります。
また、「三輪山絵図(室町時代)」には、平等寺の山側(東)に星降(ほしふり)と書かれた岩石が描かれており、その名称から磐座ではないかと推測します。そうであるならこの平等寺の影向石から星降という磐座を拝んでいたのかもしれません。
イワクラハンター 平津豊
#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #巨石文明 #古代文明 #平津豊 #イワクラハンター #奈良県 #桜井市 #三輪山 #大神神社 #平等寺 #ドルメン #影向石

本ページのリンクおよびシェアは自由です。
最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

[さらに詳細な情報]