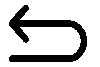173 岡山県 吉備の中山 影向石
【Introduction of Iwakura173】Visit・Photo:2025.4.13/Write:2025.5.17
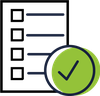
□分類:磐座(狭義の磐座)
□信仰状況:祭祀されていないが過去に信仰の形跡あり。
□岩石の形状:巨岩単体
□備考:表面に「影向石」と彫られている

□住所:岡山県岡山市北区川入
□緯度経度:34°39'41.74"N 133°50'58.65"E
(googleに入力すれば場所が表示されます)
平安時代には、吉備津神社(備中)は、正宮、本宮、新宮、内宮、岩山宮という吉備津五所大明神から形成されていました。この中の新宮は、吉備津神社(備中)から南に1キロメートル離れた場所にありました。
吉備津神社(備中)といえば、比翼入母屋造の正宮から本宮まで続く398メートルの長回廊で有名ですが、この回廊が新宮まで続いていたと云われており、吉備津神社(備中)が、いかに巨大な宗教施設だったかがわかります。
社伝によると、吉備津神社(備中)の御祭神の大吉備津彦命(別名:彦五十狭芹彦命)は吉備の中山の麓の茅葺宮に住み、281歳で亡くなった後は中山に葬られました。これが中山茶臼山古墳と考えられています。また、諸説ありますが、彦五十狭芹彦命の5代目の子孫の加夜臣奈留美命が茅葺宮に社殿を造営したのが吉備津神社(備中)の始まりであると云われています。この加夜臣が賀陽氏の祖先で、代々吉備津神社(備中)の社家を務めました。賀陽氏は、1574年に絶家していますが、臨済宗を開いた栄西禅師を輩出しています。
賀陽氏館跡が新宮跡の西400メートルの場所にあることから、新宮が本来の吉備津神社(備中)だったのではないかという考える人もいます。
確かに、この場所は東山と呼ばれ、弥生時代の集落である東山遺跡が発見されていますので、弥生時代から人々が住んでいた場所です。相対する西山は、楯築遺跡や真宮神社を含む王墓山で、東西の春分・秋分ラインで結ばれています。
新宮は、1910年に本宮に合祀されて社殿は無くなり、新宮跡には「吉備武彦命鎮座跡地」の石碑が立てられています。吉備武彦命の出自について『日本書記』に記載はありませんが、この石碑には、「本宮社御祭神ノ曾孫」と彫られています。一般的に、孝霊天皇の息子で彦五十狭芹彦命の弟である稚武彦命の息子の御鉏友耳健日子(みすきともみみたけひこ)命の息子が吉備武彦命と考えられています。
『日本書記』によると、吉備武彦は、日本武尊の東征に参加し、娘を日本武尊や応神天皇に嫁がせ、息子の御友別は吉備臣の祖となっています。
さて、新宮跡の石碑の北側には小さな本殿と拝殿が建っています。アットタウン吉備の「路傍の文化財」によると「薬師堂」と名付けられているようですが、明らかに神社様式の建物ですので、隣の真如院が新宮の摂社の一つを譲り受けて薬師堂として活用しているのかもしれません。ちなみに真如院は、明治に神仏分離が行われるまでは、新宮の神宮寺として機能していた寺院です。
この本殿の斜め後ろに影向石があります。
高さ3メートルを超える巨岩で、表面に影向石の文字が彫られています。影向(ようごう、ようこう、えごう、えいこう)とは、神仏が一時的に現れることを意味していますので、その昔、この影向石に神様が現れたと信じられたことを示しています。そのような神聖な場所だったので、新宮が造営されたのでしょう。
また、岩石の表面に「影向石」という文字を彫り込んだのは、仏教徒の仕業ではないかと思います。神聖な岩石に文字を彫るのはいただけません。
この影向石は、現在、祀られていませんが、過去には神の依り代として機能したと推測されますので、狭義の磐座に分類しました。
#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #巨石文明 #古代文明 #岡山県 #岡山市 #吉備津彦神社 #吉備津彦神社 #備前 #備中 #新宮 #吉備武彦 #影向石

本ページのリンクおよびシェアは自由です。
最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

[さらに詳細な情報]