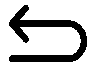180 奈良県 三輪山 綱越神社の磐座
【Introduction of Iwakura180】Visit・Photo:2013.4.29/Write:2025.7.19
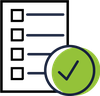
□分類:【新】磐座(狭義のイワクラ)
□信仰状況:神社に祭祀されている。
□岩石の形状:岩単体
□備考:2000年頃から祀られ始めた岩石。

□住所:奈良県桜井市三輪
□緯度経度:34°31'40.79"N 135°50'36.17"E
(googleに入力すれば場所が表示されます)
大神神社の一の大鳥居のすぐ南に綱越(つなこし)神社が鎮座しています。祓戸大神(はらえどのおおかみ)を祀っており、大神神社に参拝する前に禊祓する場所として認識されています。
大神神社のホームページには、以下のように記載されています。
「祭神 祓戸大神(はらえどのおおかみ) 例祭日 7月31日
大鳥居の南側、一の鳥居にすすむ参道入口となる三輪の馬場先に鎮座します。古く延喜式神名帳に記載され、すでに貞観元年(859)には、従五位下の神階を贈られている由緒ある古社であります。 往昔から夏越の大祓(なごしのおおはらえ)が、例祭として行われ、社名の綱越は、夏越からの転訛と考えられ、通称「御祓(おんぱら)さん」と呼ばれ親しまれています。
綱越神社例祭(おんぱら祭):大鳥居の南側に位置する摂社綱越神社で行われ、夏を無病息災で過ごすことを祈る「夏越(なごし)の祓」の祭典です。綱越神社は平安時代の『延喜式神名帳』に記載される古社で祓戸の四神を祀り、街道筋から大神神社に参拝する際に先ずお参りするお祓いの社です。神社の名前の「綱越」は「夏越し」が訛ったものと言われます。祭典名の「おんぱら祭」も「御祓い」の転訛で、神社は親しみを込めて「おんぱらさん」と呼ばれています。祭典では、大祓詞を神職が唱える間に神馬が境内を三周する「神馬(しんめ)引き」や、「水無月の 夏越しの祓へ する人は 千歳の命 延ぶといふなり」という古歌を唱えながら「茅の輪」をくぐるお祓いの神事が古式に則り行われます。 この「おんぱら祭」の日と前日の宵宮祭の日の二日間、参拝者は自由に人形(ひとがた)に託して罪・穢れを祓い遣り、息災を祈って茅の輪をくぐっておられます」
このホームページによると、大神神社は、御祭神の祓戸大神を祓戸の四神と考えており、瀬織津比売神(せおりつひめ)、速開都比売神(はやあきつひめ)、気吹戸主神(いぶきどぬし) 、速佐須良比売神(はやさすらひめ)が祀られていることになります。
大神神社では春と秋に大神祭(おおみわのまつり)が盛大に行われます。この祭りは崇神天皇が卯の日に始められたことから、卯の日神事とも呼ばれます。この祭りに参加する神主や奉仕員は、三輪川で垢離取りを行った後に、綱越神社で祓の儀を受けてから神事にたずさわったと言われています。
綱越神社は、少なくとも859年にまで遡れる古社であり式内社ですので、大神神社とは独立した神社でしたが、大神神社との関係は深かったと考えられます。1877年に大神神社の境外摂社となります。
また、ホームページでは「綱越」は「夏越し」が訛ったものとの説が記載されていますが、注連縄を通して三輪山の神を拝していたとする説もあります。近くの素戔嗚神社には勧請縄の風習もありますので、「綱越」をそのまま「綱を越して三輪山を拝する場所」と解釈する考えの方が納得できます。さらに、筆者は、三輪山だけではなく、三輪山から昇る朝日を拝していたと考えます。綱越神社から見て三輪山は、大神神社が拘っている卯の方向(東)にありますが、三輪山の頂上は68度の方向にあり、真東から22度ズレています。では、綱越神社から見て、467メートルの三輪山の頂上から太陽が昇るのはいつになるのでしょうか。859年で計算すると7月18日の5時48分にちょうど三輪山の山頂から太陽が顔を出します。この7月18日はユリウス暦ですが、2025年で計算しても7月20日の5時50分となります。一方、綱越神社の最大のお祭りであるのおんぱら祭りは2025年7月31日に行われます。この日程が近いことから、「綱越神社では注連縄を通して三輪山の頂上から昇る太陽を崇拝していた」という考えは、あながち間違っていないのではないかと思います。
綱越神社の社殿の北側の二本の木の間に注連縄が巻かれた岩があります。『三輪山周辺の考古学(桜井市文化財協会、2000年)』には、「磐座」と表記されていますが、寺沢薫『大神神社境内地発掘調査報告書(1984)』 や樋口清之『三輪山上に於ける巨石群(1974)』など古い文献に「綱越神社の磐座」に関する記述は見当たりません。1980年頃から何度も大神神社に参拝している筆者自身も綱越神社で磐座を見た記憶がありません。
つまり、古代から岩石祭祀が行われていた岩石ではなく、2000年頃から祀られだした磐座と推測します。綱越神社が注連縄を付けて祭祀していますので「磐座」に分類しますが、古代から祭祀されている磐座と区別するために【新】を付けることにします。
イワクラハンター 平津豊
#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #巨石文明 #古代文明 #平津豊 #イワクラハンター #奈良県 #桜井市 #三輪山 #大神神社 #綱越神社 #おんぱら

本ページのリンクおよびシェアは自由です。
最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

[さらに詳細な情報]