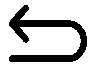179 奈良県 三輪山 九日社の陰陽石
【Introduction of Iwakura179】Visit・Photo:2013.4.29/Write:2025.7.5

□分類:石神(広義のイワクラ)、陰陽石
□信仰状況:神社に祭祀されている。
□岩石の形状:双石、男女の生殖器に似た石
□備考:人工物

□住所:奈良県桜井市芝
□緯度経度:34°32'6.489"N 135°50'23.069"E
(googleに入力すれば場所が表示されます)
桜井市箸中のホケノ山古墳の近くに国津神社があります。「地主の森」と呼ばれた地域に鎮座するこの神社には、正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊(まさかあかつかちはやひあめのおしほのみみのみこと)、天穂日命(あめのほひのみこと)、天津彦根命(あまつひこねのみこと)、活津彦根命(いくつひこねのみこと)、熊野櫲樟日命(くまのくすひのみこと)が祀られています。
この五柱の神は、天照大神と素盞鳴の誓約(うけい)で生まれた神々です。
その場面は、『日本書記』には以下のように書かれています。
「素戔嗚尊對曰「吾元無黑心。但父母已有嚴勅、將永就乎根國。如不與姉相見、吾何能敢去。是以、跋渉雲霧、遠自來參。不意、阿姉翻起嚴顏。」于時、天照大神復問曰「若然者、將何以明爾之赤心也。」對曰「請與姉共誓。夫誓約之中誓約之中、此云宇氣譬能美儺箇必當生子。如吾所生是女者則可以爲有濁心、若是男者則可以爲有淸心。」於是、天照大神、乃索取素戔嗚尊十握劒、打折爲三段、濯於天眞名井、𪗾然咀嚼𪗾然咀嚼、此云佐我彌爾加武而吹棄氣噴之狹霧吹棄氣噴之狹霧、此云浮枳于都屢伊浮岐能佐擬理所生神、號曰田心姫。次湍津姫、次市杵嶋姫、凡三女矣。既而、素戔嗚尊、乞取天照大神髻鬘及腕所纒八坂瓊之五百箇御統、濯於天眞名井、𪗾然咀嚼、而吹棄氣噴之狹霧所生神、號曰正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊。次天穗日命是出雲臣・土師連等祖也、次天津彥根命是凡川內直・山代直等祖也、次活津彥根命、次熊野櫲樟日命、凡五男矣。是時、天照大神勅曰「原其物根、則八坂瓊之五百箇御統者是吾物也。故、彼五男神、悉是吾兒。」乃取而子養焉。又勅曰「其十握劒者、是素戔嗚尊物也。故、此三女神、悉是爾兒。」便授之素戔嗚尊、此則筑紫胸肩君等所祭神是也。」
天照大神が素戔嗚尊の十握剣を噛み砕いて生まれたのが三柱の女神(田心姫、湍津姫、市杵嶋姫)で素戔嗚尊の子供。素戔嗚尊が天照大神の八坂瓊勾玉を噛み砕いて生まれたのが五柱の男神(正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野櫲樟日命)で天照大神の子供であるという内容です。
この国津神社から600メートル南西の芝にもう一つの国津神社が鎮座しています。こちらの御祭神は、多紀理比賣命(たきりひめのみこと)、狭依理比賣命(さよりひめのみこと)、多岐津比賣命(たきつひめのみこと)となっていますので、纏向川を挟んで上流に五柱の男神を祀る国津神社があり、下流に三柱の女神を祀る国津神社があるという事になります。明らかに意図して2つの神社を配置したと考えられます。
国津神社の説明書にも以下のように書かれています。
「当國津神社は、古来より「地主の森」といい、天照大神の御子神五柱を祭神としています。この男神五柱は、『記紀』神話によると、素盞鳴尊が天照大神と天の安河を中にはさんで誓約をしたとき、天照大神の玉を物実として成り出た神であります。ちなみに纏向川下流の芝の国津神社(九日神社)には、素盞鳴尊の剣を物実としてうまれた奥津島比売、市杵島比売、多岐津比売の三女神を祭祀しています。この箸中と芝で、神の山三輪山を水源とする纏向川をはさみ、二神の誓約によって成り出た神をそれぞれ祭神としていることに、古代伝承の原景を見る思いがし、敬神の念を禁じ得ません。なお古来より毎年八月二十八日には、大字箸中と芝が相集い、三輪山の麓に鎮座する檜原神社(祭神・天照大神)の大祭を執行しています。また『日本書記』崇神天皇六年の条に「天照大神・倭大国魂二神を、天皇の大殿の内に並祭る。然して其の神の勢いを畏りてともに住みたまふに安からず。故、天照大神を以ては、豊鍬入姫命に託けまつりて、倭の笠縫邑に祭る」とあり、ここ箸中の東、三輪山麓の檜原の地は天照大神の伊勢鎮座以前の宮居のあった笠縫邑の伝承地となっています。天照大神の祭祀に奉じた豊鍬入姫命は崇神天皇の皇女で、その墓所が國津神社裏のホケノ山古墳であるという伝承が地元に伝わっています。」
芝の国津神社は九日社(くにちしゃ)とも呼ばれています。「九日」という名称の由来については、国津(くにつ)からの転訛、9月9日の重陽の節句の「九日(くにち)」(九州北部では「くんち」に転訛)、収穫物を神に供える日の「供日(くにち)」、朝に昇る太陽を示す旭が分割されて表記された、など諸説あります。
神社名については、御祭神が天照大神と素盞鳴尊の子供達であるのに、「国津神社」もおかしな話です。五柱の男神と三柱の女神は、高天原出身の天津神ですから、「天津神社」とするべきです。「くにち」の意味は分かりませんが、「くにち」という名前が先にあり、「国津」という文字を当てたのではないかと考えます。
さて、この九日社には、小さな石が2つ並んで祀られています。
『大神神社境内地発掘調査報告書(寺沢薫、奈良県立橿原考古学研究所編集、1984)』 によると「磐座」と表記されています。しかし、『三輪山上に於ける巨石群(樋口清之、1927)』では「リンガとヨナの形でファリシズムの痕蹟」と書かれ、『三輪山周辺の考古学(桜井市文化財協会、2000)』では「[磐座]陰陽石」と記載されています。
この双石の形状は男根と女陰を表したもので「陰陽石」です。「陰陽石」は、男女の生殖器に似た岩石を子宝及び安産祈願の神として崇めるもので「磐座」ではなく「石神」の分類になります。
この陰陽石がいつ頃から信仰されたのかはわかりませんが、民間による子宝祈願や安産祈願の信仰が継続している岩石と推測します。
イワクラハンター 平津豊
#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #巨石文明 #古代文明 #平津豊 #イワクラハンター #奈良県 #桜井市 #三輪山 #大神神社 #国津神社 #九日社 #陰陽石

本ページのリンクおよびシェアは自由です。
最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

[さらに詳細な情報]