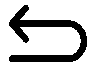134 三重県 磯部町の鸚鵡岩
【Introduction of Iwakura 134】

□分類:岩石信仰(広義のイワクラ)
□信仰状況:民間に祭祀されている。
□岩石の形状:岩盤
□備考:

□住所:三重県志摩市磯部町恵利原
□緯度経度:34°23'19.679"N 136°47'49.980"E
(googleに入力すれば場所が表示されます)
伊勢の内宮から伊勢街道を通って、伊雑宮に向かう途中に見える岩山が和合山で、この岩山の麓に鸚鵡岩があります。1797年の『伊勢参宮名所図会』にも描かれている有名な岩石です。『伊勢参宮名所図会』には、鸚鵡岩と書いて「あふむいし」とるびが付けられています。高さ31メートル、幅127メートルの岩盤で、「語り場」で話すと、50メートル離れた「聞き場」に居る人にその声がはっきりと聞こえることから鸚鵡岩と名付けられています。岩盤で跳ね返った音が遠くまで伝播する現象で、江戸時代に発見されたと言われています。また、この岩盤の前には玉依姫命が祀られており、近くには「倭姫機織場」という場所があります。さらに、江戸時代に書かれた百井塘雨の『笈埃随筆』の4巻では、御師(おんし)が和合山と稚日女尊の関係を語っていますが、これらの祭祀は、江戸時代以降の後付けと考えられます。おそらく、伊雑宮への参拝者が通る街道の側にあるこの鸚鵡岩を神秘の場所として伊雑宮が利用したのではないかと思われます。
伊雑宮は、1531年に的矢氏が九鬼浄隆に滅ぼされ、伊雑の神戸が九鬼氏に横領されると、経済的基盤を失って没落していきました。伊雑宮は再興の訴えを度々起こしますが、その請願活動の中で伊雑宮の重要性を強調するために、1646年には「伊勢三宮」という表現で内宮や外宮と同格であることを主張し始め、1658年には、ついに伊雑は内宮の本家という主張を行ないました。これらの伊雑宮再興活動の一環として、この鸚鵡岩も利用された可能性が高いと思います。
鸚鵡岩の「山びこ現象」については、自然に形成された現象と考えています。また、祭祀については、伊雑宮から1.5キロメートルしか離れていない和合山に古代からの信仰が存在した可能性はありますが、その記録はありません。しかしながら、現在は、鸚鵡岩に玉依姫命が祀られていることから岩石信仰に分類しました。
なお、2016年にイワクラ学会がこの鸚鵡岩を訪れたことで、地元の人により木々が伐採され、和合山が『伊勢参宮名所図会』に描かれているような岩山に戻りました。
#イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #巨石文明 #古代文明 #三重県 #神宮 #伊勢神宮 #伊雑宮 #鸚鵡岩 #おうむ岩

本ページのリンクおよびシェアは自由です。
最近、本ページの内容をそのままコピーして転載しているサイトを見かけますが、本ページの内容、テキスト、画像等の無断転載(複製して他の媒体に公開)を固く禁じます。特に、まとめサイト等への使用を厳禁いたします。また、出典を明記しての引用は許可していますが、以下の引用のルールに則って行ってください。それ以外は「盗用」「剽窃」となります。1.引用元が明示されていること/2.引用部分が明確に区別されていること/3.引用部分を修正していないこと/4.引用する必然性があること/5.分量的にも内容的にも、自分の著作部分が主で、引用部分が従であること

[さらに詳細な情報]